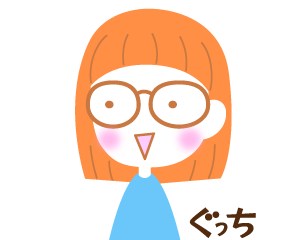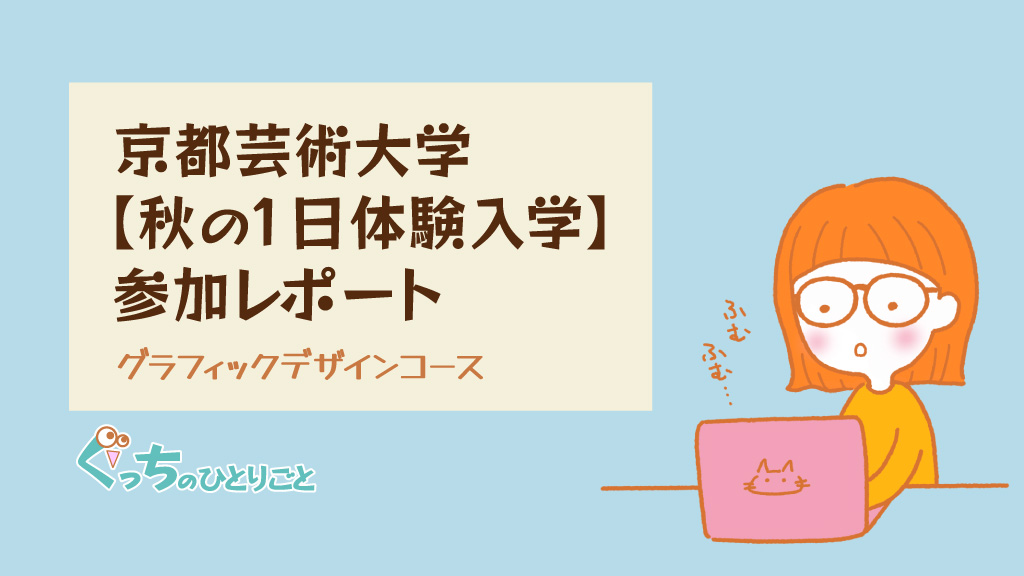
こんにちはー、ぐっちです。
11月18日(土)に開催された、京都芸術大学【秋の1日体験入学】グラフィックデザインコース体験授業に参加しました!
参加レポート、さっそくいってみよ〜
京都芸術大学【秋の一日体験入学】グラフィックデザインコース体験授業
担当教員
-
荒川慎一
授業内容
グラフィックデザインの入口―ロゴデザインを紐解く―グラフィックデザインが扱う専門領域は広く、日常のさまざまな場面で活かされています。今回は入門編として、きっとみなさんも日常的に目にしたことがある企業やサービスの有名ロゴを題材にしながら、そのデザインに隠されたアイデアや秘密を紐解いていきます。近年ではデジタルデバイスに表示させるために、透過するロゴや動くロゴ、多種展開するロゴまで登場しています。そんなロゴデザインを紹介しながら、グラフィックデザインの面白さや奥深さについて触れていきます。
参加レポート
ロゴデザインの秘密を探る
既存のロゴマークを見ながら、ロゴデザインにまつわるお話をときにはクイズも交えながらお話してくださいました。
全てのロゴマークにストーリーがあり、思いや意味がある。
たくさん紹介していただいた中で、私が特に印象に残ったロゴマークを3つご紹介します。
1.メルボルン・シティのMのロゴ
形は決まってるんだけど、中のデザインはいろいろ。
「多様性」を表現してるらしい。ぱっと見違うものに見えるんだけど、そのMの形を見たらみんな「メルボルンのロゴだ」ってわかる。
ロゴって、カチッ!と形が決まってて、いじったらダメなものだ、って認識だったんだけど、こういうのもあるんだー、って面白かった。
「Mのロゴがたくさん集まるほど楽しい雰囲気になる」
って言う先生の言葉にも納得。いろんな色やデザインとか見た目だけじゃなくて、思想や価値観、そういういろいろなモノがたくさん集まって「楽しい」はとてもいいメッセージだと思った。
City of Melbourne ホームページ↓
英語のサイト。少し重いかも・・・?興味のある人は見てみてほしい。
全然関係ないんだけど、City of Melbourne のホームページ見るの楽しかった。
全部英語だから全然読めないんだけど、海外の町のホームページって日本のとは違った雰囲気だったりで面白い。町の地図とかあって、わかんないんだけど、ここら辺に住んだらどんな感じなのかな〜とか想像しちゃう。
おかげでブログ書くの全然進まなくなった。(言い訳です)
2.2028年LAオリンピックのロゴ
Lと28は黒の太字で固定。Aのイラストは可変的で、アーティストやアスリートたち26人による複数のデザインになってる。
オリンピックのロゴでデザインの一部が動くのは史上初らしい。
ロサンゼルスで開催される2028年オリンピック・パラリンピックの組織委員会が公式ロゴを発表しました!でも、ロゴは一つだけではないんですよ!ダイナミックな26種類のロゴがあり、それぞれがロサンゼルスの多様性と力強さを強調しています。#LA28pic.twitter.com/WbAFFHDUXm
— アメリカ大使館 (@usembassytokyo) 2020年9月2日
3.EXPO2025のロゴ
話題になった「ミャクミャク」のモチーフになったロゴですね。
正直最初見た時は「うぅぉー・・・・・」って思った記憶があるんだけど、今回の授業でデザインシステムの動画と説明見て納得。
見事にロゴと融合されてて、そういうことだったのか!ってなる。
「個のいのち」が成長して、他の「個のいのち」(異なる個性)と出会って集合体になり融け合っていく様子がよくわかる動画。
繋がるだけじゃなくて、「出会ったり別れたりしながら変化し続けるいのち」
いろんなモノ・コトと出会って成長したり進化していく。「いのちの循環」
1枚の大きなグラフィックも切り取る場所によって見え方が全然かわるの。でも、違う絵を見ているようで実はひとつの同じ世界を見てるんだよ、的なのもいいな、と思った。
ちょっと私の言葉じゃ伝わんないですよね。ぜひこのページ見てみてほしいです。デザインシステムについて説明されてて、とりあえずサイトのデザインがかわいい。
なんだか最後はロゴの話じゃなくなっちゃった気もする・・・
「本で勉強」から「動画学習」に、「Blog」から「Vlog」に。
いろいろなものが動くものに変わっていってる印象だけど、ロゴマークもそういう流れになっていくのかな?
いいロゴとは何か?
・いいロゴは、「最小の形状」で、「最大の情報」を伝達する
・いいロゴは、繊細で美しくも、力強さと存在感を併せ持つ
・いいロゴは、組織のカルチャーやビジョンの結晶である
・いいロゴは、組織の活動をより加速させ、拡大することを手伝う
・いいロゴは、最高のレバレッジをうみだす
デザインを上達させるコツは?
好奇心に任せて街を歩く。街にあるもの、身の回りにあるもの全て誰かの制作物。
なんでこのデザインにしたんだろう?と考えてみる。「ただ見る」ではなく「観察する」好奇心をもって本を読んだり映像を見てみる。
出かけたときにも興味のあるとこ全部観察する。
例えば映画館なら、サインデザインやパンフレット、タイトルロゴなど観察してみる。なんならデッサンしてみる。
観察眼の鍛え方は?
好奇心と行動力。
なんでこうしたのかな?自分ならこうするな。と感じたとき、基本は自分のことを信じる。他の人がいいと言っていても自分は違うと思う感覚も大切にする。
5W1Hの問いかけ。なんでここにあるの?誰に向けて作ったの?なんのために?
子どもみたいにナゼナゼマンになってみる。
感想まとめ
私、ロゴって1番難しいと思ってるんです。だから自分なんかが手を出せるわけがない、って遠ざけてたとこがあって。ロゴの本とかもあんま見ないようにしてたの(笑)
今回の授業を受けて、あらためてロゴって奥が深くて難しい!って思った。
でも、ひとつのデザインから歴史とか時代背景とかトレンドとか制作者の思いとかに思いを馳せるのは楽しいと思った。
これはデザインの勉強に限らず、なんでも自分の好きなこと・興味のあることを深めるのにも通じるな、と思った。
私もナゼナゼマンになろうと思う。
あと、デザイン学ぶとき、
「よし!Illustratorの操作完璧にするぞ!」
ってツールの操作極めようとしちゃいがちなんだけど、私頭でっかちで。
でもそれはあくまでも「方法」であって、そのツールを使って自分のことや周りの問題を解決したりハッピーにすることがデザインの本質で。
解像度上げて自分や周りの人の人生豊かにしたいと思いました。
以上!
長文・乱文になってしまいましたが、最後まで読んでくださりありがとうございました!
ではまた〜